2008年06月05日
歯の衛生週間シリーズ4
今日は、4回目で「歯周病と全身疾患」です。
歯周病がいろいろな全身の病気を引き起こしたり
悪化させたるすることがわかってきています。
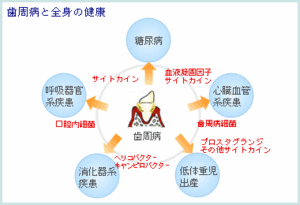 岡山大学
岡山大学
今まで、多くの方が歯周病が単に歯肉の病気と思っていられたと思います。
しかし、歯周病という炎症性疾患によって産生される物質や細菌そのものによって
いろいろな悪影響を起こしてしまいます。
お年寄りや障害のお持ちの方は、嚥下機能が弱くなっているかたもおられます。
そんな場合、食道ではなく気管に誤って入ってしまい、
歯周病の原因菌が肺や気管支に感染して肺炎を起こしてしまうことがあります。(誤嚥性肺炎)
お口の中の環境が悪いとその危険が高まってしまいます。
そのため、日ごろより口腔内を健康に保つことが大切です。
もしも、寝たきりや身体が不自由になった場合も、家族の協力と
歯科医師や歯科衛生士による口腔ケアをうけてお口の健康を維持できるようにしましょう。
妊娠すると女性ホルモンの変化やつわりや偏食などにより
口腔の環境が悪化し歯肉炎を発症しやすいことはわかっています。(妊娠性歯肉炎)
そればかりでなく、妊娠中に歯周病に罹患していると、毒素や炎症性物質が血液中から胎盤に入り、低体重児出産や早産のリスクが高まることが明らかになっています。
妊娠中はもとより、日ごろからきちんと歯磨きをして歯周病を予防していくことが大切です。
心疾患は日本の3大死亡原因の1つに挙げられています。
歯周病により歯肉が腫脹し出血しやすい環境だと、歯周病菌が血流に乗って冠動脈に感染すると
原因菌が産生する炎症性物質や毒素が血栓を作り、動脈硬化(アテローム性動脈硬化症)を発症させる可能性が指摘されています。
また、口腔の細菌が血流に乗り細菌性心内膜炎を起こすといわれています。
糖尿病の方は、感染しやすく傷の治りが遅くなることもよく知られています。
そのため、糖尿病の方は歯周病になりやすくまた治癒も遅れがちになります。
また、歯周病菌の毒素がインスリンの働きを悪くし、血糖値を下がりにくくし、
結果的に糖尿病の発症につながる可能性があると考えられています。
このように、歯周病を含め口の中の細菌が全身の病気に大きく関与していることがわかっています。
体の健康を維持するためにも、お口の健康は大切です。
そのためにも、おうちでのセルフケア、定期的な歯科医院でのプロフェッショナルケアを受けることお勧めします。
歯周病がいろいろな全身の病気を引き起こしたり
悪化させたるすることがわかってきています。
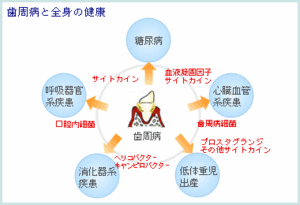 岡山大学
岡山大学今まで、多くの方が歯周病が単に歯肉の病気と思っていられたと思います。
しかし、歯周病という炎症性疾患によって産生される物質や細菌そのものによって
いろいろな悪影響を起こしてしまいます。
お年寄りや障害のお持ちの方は、嚥下機能が弱くなっているかたもおられます。
そんな場合、食道ではなく気管に誤って入ってしまい、
歯周病の原因菌が肺や気管支に感染して肺炎を起こしてしまうことがあります。(誤嚥性肺炎)
お口の中の環境が悪いとその危険が高まってしまいます。
そのため、日ごろより口腔内を健康に保つことが大切です。
もしも、寝たきりや身体が不自由になった場合も、家族の協力と
歯科医師や歯科衛生士による口腔ケアをうけてお口の健康を維持できるようにしましょう。
妊娠すると女性ホルモンの変化やつわりや偏食などにより
口腔の環境が悪化し歯肉炎を発症しやすいことはわかっています。(妊娠性歯肉炎)
そればかりでなく、妊娠中に歯周病に罹患していると、毒素や炎症性物質が血液中から胎盤に入り、低体重児出産や早産のリスクが高まることが明らかになっています。
妊娠中はもとより、日ごろからきちんと歯磨きをして歯周病を予防していくことが大切です。
心疾患は日本の3大死亡原因の1つに挙げられています。
歯周病により歯肉が腫脹し出血しやすい環境だと、歯周病菌が血流に乗って冠動脈に感染すると
原因菌が産生する炎症性物質や毒素が血栓を作り、動脈硬化(アテローム性動脈硬化症)を発症させる可能性が指摘されています。
また、口腔の細菌が血流に乗り細菌性心内膜炎を起こすといわれています。
糖尿病の方は、感染しやすく傷の治りが遅くなることもよく知られています。
そのため、糖尿病の方は歯周病になりやすくまた治癒も遅れがちになります。
また、歯周病菌の毒素がインスリンの働きを悪くし、血糖値を下がりにくくし、
結果的に糖尿病の発症につながる可能性があると考えられています。
このように、歯周病を含め口の中の細菌が全身の病気に大きく関与していることがわかっています。
体の健康を維持するためにも、お口の健康は大切です。
そのためにも、おうちでのセルフケア、定期的な歯科医院でのプロフェッショナルケアを受けることお勧めします。
2008年06月05日
ちょっとまじめな話3
日本の財政についての諮問機関として、財務相の諮問機関「財政制度等審議会」があります。
この財政制度等審議会が、6月3日、「2009年度予算編成の基本的考え方」(建議)をまとめ、額賀福志郎財務相に提出しました。
これによると、社会保障費の伸びを毎年2200億円ずつ圧縮する政府方針について、「続けるべきと思う」との認識を示し、11年度までの社会保障費1.1兆円抑制目標を達成するようにとしています。
この理由として、歳出改革の方針を後退させて将来世代に負担を先送りすれば、「国民の不安は増幅しかねない」との理由です。
確かに、無駄な歳出は防ぐことは大切ですが、社会保障費を抑制することは、今の後期高齢者問題にしてもより社会保障費の大きな抑制はより不安を招きかねないと思いますがいかがでしょうか?
また、それに伴い次のようなことも・・・・。
健康保険から給付される医療のうち、一定の金額までは医療保険の適用を免除して全額を患者の自己負担とする「保険免責制」の導入を検討。
これは、医療費の一定額まで全額患者負担で、ということで仮に1000円までを免責にして全額自己負担にすると、現在の3割負担(後期高齢者1割)が実質4.1割(後期高齢者2.2割)になると試算されています。形だけ3割にして実質は患者負担を増やすというのはいかがかと思いますが如何に。
このようなことが話し合われていることは、あまり新聞やニュースなどでも流れません。
後期高齢者制度にしても、実質始まる少し前にマスコミが騒ぎ始めたことを考えると
もっと早く情報を流してもらいたいものです。
この財政制度等審議会が、6月3日、「2009年度予算編成の基本的考え方」(建議)をまとめ、額賀福志郎財務相に提出しました。
これによると、社会保障費の伸びを毎年2200億円ずつ圧縮する政府方針について、「続けるべきと思う」との認識を示し、11年度までの社会保障費1.1兆円抑制目標を達成するようにとしています。
この理由として、歳出改革の方針を後退させて将来世代に負担を先送りすれば、「国民の不安は増幅しかねない」との理由です。
確かに、無駄な歳出は防ぐことは大切ですが、社会保障費を抑制することは、今の後期高齢者問題にしてもより社会保障費の大きな抑制はより不安を招きかねないと思いますがいかがでしょうか?
また、それに伴い次のようなことも・・・・。
健康保険から給付される医療のうち、一定の金額までは医療保険の適用を免除して全額を患者の自己負担とする「保険免責制」の導入を検討。
これは、医療費の一定額まで全額患者負担で、ということで仮に1000円までを免責にして全額自己負担にすると、現在の3割負担(後期高齢者1割)が実質4.1割(後期高齢者2.2割)になると試算されています。形だけ3割にして実質は患者負担を増やすというのはいかがかと思いますが如何に。
このようなことが話し合われていることは、あまり新聞やニュースなどでも流れません。
後期高齢者制度にしても、実質始まる少し前にマスコミが騒ぎ始めたことを考えると
もっと早く情報を流してもらいたいものです。
2008年06月05日
歯の衛生週間シリーズ3
三回目は、「歯周炎」についてです。
歯周炎は、歯の周囲を支えている組織が破壊されていく病気です。
主な原因は、歯に付着しているプラークにいる歯周病誘発菌によって引き起こされます。
この菌が産生する毒素で歯茎を腫らし、血や膿を出したり、歯の周りの骨を溶かしたりします。
そのため、歯肉から出血したり、口臭がしたり、進行すると歯がぐらぐらしていきます。
このように、歯周病は細菌による感染症なので、大きな原因であるプラークをきちんと除去することが
予防の第一歩ですから、毎食後の歯みがきは重要なのです。

この歯周病は、
人類が誕生してから今日までで一番感染者数の多い感染症としてギネスに載っています。
日本でも、平成11年度の歯科疾患実態調査によると、口の中に何らかの歯周病の症状がある人の割合は5~14歳の子どもですでに37%、15~24歳の若者で65%、45~54歳の中年世代では90%近くに達しています。
ただ、若いうちは歯周病の症状らしい症状が現れにくいため見過ごされることが多く、
年齢を重ねるに従い、症状が進行し、歯がぐらぐらしたり、物を噛んだときに痛みが出たり、歯肉が腫れるなどの自覚症状が顕著になり歯科医院に受診すると、手遅れに近い状態になっているケースも多いのです。
できれば、歯周病の予防のために若いうちから歯科医院で定期的な健診と予防処置を受けてもらいたいと思います。
歯周病の進行には個人差があり、
自分の持っている免疫機能の状態、喫煙、全身疾患の有無等で大きく左右されるのです。
特に、喫煙習慣の有無が大きく影響を与えていることがはっきりしており、
非喫煙者に比べ喫煙者の歯周病罹患率は非常に高いことがわかっています。
できたら、健康な歯肉を維持するためにも禁煙してもらいたいと思います。
次回は、歯周病と全身疾患とのかかわりについて書いてみようと思います。
歯周炎は、歯の周囲を支えている組織が破壊されていく病気です。
主な原因は、歯に付着しているプラークにいる歯周病誘発菌によって引き起こされます。
この菌が産生する毒素で歯茎を腫らし、血や膿を出したり、歯の周りの骨を溶かしたりします。
そのため、歯肉から出血したり、口臭がしたり、進行すると歯がぐらぐらしていきます。
このように、歯周病は細菌による感染症なので、大きな原因であるプラークをきちんと除去することが
予防の第一歩ですから、毎食後の歯みがきは重要なのです。

この歯周病は、
人類が誕生してから今日までで一番感染者数の多い感染症としてギネスに載っています。
日本でも、平成11年度の歯科疾患実態調査によると、口の中に何らかの歯周病の症状がある人の割合は5~14歳の子どもですでに37%、15~24歳の若者で65%、45~54歳の中年世代では90%近くに達しています。
ただ、若いうちは歯周病の症状らしい症状が現れにくいため見過ごされることが多く、
年齢を重ねるに従い、症状が進行し、歯がぐらぐらしたり、物を噛んだときに痛みが出たり、歯肉が腫れるなどの自覚症状が顕著になり歯科医院に受診すると、手遅れに近い状態になっているケースも多いのです。
できれば、歯周病の予防のために若いうちから歯科医院で定期的な健診と予防処置を受けてもらいたいと思います。
歯周病の進行には個人差があり、
自分の持っている免疫機能の状態、喫煙、全身疾患の有無等で大きく左右されるのです。
特に、喫煙習慣の有無が大きく影響を与えていることがはっきりしており、
非喫煙者に比べ喫煙者の歯周病罹患率は非常に高いことがわかっています。
できたら、健康な歯肉を維持するためにも禁煙してもらいたいと思います。
次回は、歯周病と全身疾患とのかかわりについて書いてみようと思います。
タグ :歯周病









